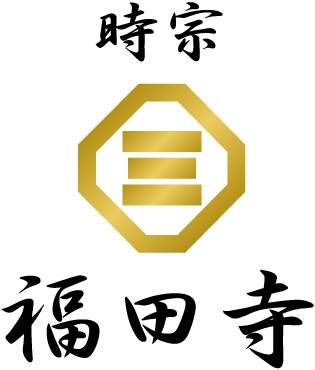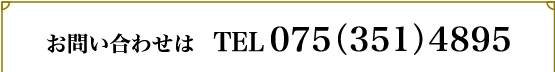福田寺は山号を東岡山といい、文永元年(1264)、鎌倉幕府6代将軍・一品宗尊親王(後嵯峨天皇の皇子)により創建されました。開山は覚阿堯空上人です。
京都東山の渋谷にあったので渋谷道場、滑谷道場(汁谷道場)とも呼ばれました。
創建後まもなく、京都に遊行された一遍上人の御化益により、時宗に改宗しました。
そして、豊国神社の造営に際し、東山渋谷から現在地へ移転しました。また地所として高倉万寿寺(現在、福田寺町)を賜ったといいます。
寛文年間(1661-1673)には、「乳房地蔵尊」が祀られる道場として、「洛陽四十八所地蔵霊場」のひとつに指定されました。「洛陽四十八所地蔵霊場」とは、霊元天皇の命で僧・宝山が指定した48ヶ寺を指します。
現在の本堂・山門は江戸期のものです。
◎“福田”の由来はコチラ
Fukudenji is a temple of the Jishu sect of Buddhism built in 1264. It was founded by Prince Munetaka , the 6th Shogun of Kamakura (Prince of Emperor Gosaga).
Since it was first built in Shibutani in Higashiyama, Kyoto, it was also called Shibutani Dojo. Dojo originally meant a place of Buddhist practice, a place to practice Nembutsu(chant the name of buddha).
It was moved to its present location in the 16th century when Toyokuni Shrine was built.
The present main hall and temple gate are from the Edo period.


皇族の出家者が住職を務めた門跡寺院の証しである筋塀。3本の定規筋が入っているものは京都でも非常に珍しい。
御本尊は弥陀三尊(阿弥陀如来、観音菩薩、勢至菩薩)です。
阿弥陀如来像は、恵信僧都作、安阿弥(快慶)作等と伝わり、鎌倉期の優作と評されます。上半身は三尺阿弥陀には珍しく覆肩衣(内側の衣)を着けず、衲衣(袈裟)のみです(「片袖の弥陀」とも)。両脇侍は江戸期の作です。
また、乳房地蔵菩薩像が本堂内に安置されています。
The principal image of the temple is the Amida Nyorai Buddha.Amida Nyorai is the head of the Pure Land of Ultimate Bliss and has vowed to save all those who chant “Namu Amida Butsu” (I take refuge in Amida Nyorai).
This statue of Amida Nyorai is considered an excellent work from the Kamakura period (12th-14th century). The statue is also called “Kata-sode-no-Mitabha (Amitabha with one sleeve)” because the right sleeve does not hang down, which was rare for a standing statue of this period.


本堂内には小野篁作と伝わる乳房地蔵菩薩像が安置されています。
この地蔵尊は、お乳の出が良くなる・お乳の病を癒す等、乳房守護の御利益から「洛陽四十八所地蔵霊場」の第44番札所にも指定され、多くの人々から信仰されてきました。
また、この地蔵菩薩像はいつ頃からか行方が分からなくなっていましたが、明治時代のはじめに「髙島屋」創業者の初代・飯田新七が夢想し地蔵尊を発見、当山に奉納しました。
御詠歌(霊元天皇 御製)
「嬰児をわきて 恵みのいちしるき 乳房の求め かなはぬはなし」
(この地蔵尊は特に赤ん坊への恩恵がいちじるしい。乳を求めれば必ず叶う。)
Chibusa(Breast) Jizo Bodhisattva.
Chibusa Jizo odhisattva is enshrined on the right side of the main hall. This Jizo is believed to protect the breast by “improving the flow of milk” and “Cure breast diseases”
A poem composed by Emperor Reigen
“Midorigo wo wakite megumi no ichisiruki Chibusa no motome kanawanuha nashi”
(Meaning: This Jizo’s blessings are especially beneficial to babies. If you ask for milk, it will surely come true.)

| 1月1日 | 修正会 |
|---|---|
| 4月8日 | 釈尊降誕会(花まつり) |
| 3月22日 | 春の彼岸施餓鬼法要(午後2時) |
| 7・8月 | 盂蘭盆会棚経 |
| 9月22日 | 秋の彼岸施餓鬼法要(午後2時) |
| 毎月第4土曜日 | 写経会(午後2時より) |
時宗は、一遍上人を宗祖、真教上人を二祖として仰ぎ、両祖師のみ教えを基に、
名号「南無阿弥陀仏」を拠りどころにする浄土門の一流です。

| 名称 | 時宗 |
|---|---|
| 宗祖 | 證誠大師 一遍上人(智真) |
| 二祖 | 他阿弥陀仏(他阿) 真教上人 |
| 開宗 | 文永11年(1274) |
| 総本山 | 清浄光寺(通称:遊行寺)- 神奈川県藤沢市 |
| 本尊 | 阿弥陀仏(阿弥陀如来) |
| 所依経論 (お経) |
浄土三部経(「無量寿経」・「観無量寿経」・「阿弥陀経」)をより所にします。読経ではそのほか「六時礼讃」などもお読みします。 |
一遍上人も真教上人も教団に所属している僧尼を「時衆」と呼んでいます。
これは浄土教の祖師である善導大師が自らの門弟を「時衆」と呼んだことに由来します。
一日24時間を4時間ごとに分割した勤行(六時礼讃)や不断念仏などの法要を一定期間行うときには、時間で僧尼を交代させる必要があり、交代要員の人数と時間は定められていました。その要員が「時衆」です。
「時衆」は本来個々の僧尼を示す言葉ですが、他教団が使わなくなり、一遍上人を宗祖とする「時衆」だけが使用するようになり、教団の名称として通用するようになりました。
江戸時代に入ると「衆」が「宗」に代わり、「時宗」が宗派の名として確定されます。
そのため、一遍上人を宗祖とする僧尼衆を表すときに、江戸時代より前の場合は「時衆」、江戸時代以降の場合は「時宗」と呼ぶ慣わしがあります。
また、時宗の「時」は『阿弥陀経』の説示である「臨命終時」に拠るとする教説もあります。一遍上人は臨終のお念仏を強調されましたが、これは単に命が尽きる時という意味ではありません。臨終は即ち平生であり、平生は即ち臨終です。つまり、生涯を終えるまで連続する“ただ今”を常に臨終の時と心得て、念仏するのが大事だとおっしゃられたのです。

更に詳しく知る→「時宗」公式ホームページ